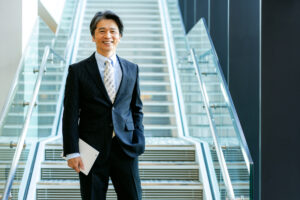宅建業免許は個人・法人どちらが良い?登記との関係も解説

不動産業を始めるにあたり必須となるのが「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」です。
取得にあたっては、個人として申請する方法と、法人を設立して申請する方法の2つがあります。
どちらを選ぶべきかは、開業規模や将来の展望によって変わります。
また、免許申請と法人登記との関係も理解しておく必要があります。
この記事では、宅建業免許を個人と法人どちらで取得すべきか、その違いと登記との関係を詳しく解説します。
宅建業免許とは何か
宅建業免許の基本的な仕組み
宅建業免許とは、不動産の売買や賃貸の仲介などを業として行う際に必要な免許です。
免許を持たずに取引を行うことは法律で禁止されており、違反すると罰則があります。
免許は国土交通大臣または都道府県知事から交付され、5年ごとの更新が義務付けられています。
個人と法人での申請の違い
宅建業免許は、個人でも法人でも取得可能です。個人であれば代表者個人が申請主体となり、法人であれば法人そのものが申請主体となります。
どちらの場合でも「専任の宅地建物取引士」を1名以上配置する必要があり、免許要件自体に大きな差はありません。違いは主に信用力や運営体制にあります。
個人で宅建業免許を取得する場合
取得に必要な条件と手続き
個人で宅建業免許を取得する場合、税務署に「開業届」を提出し、事務所を準備したうえで都道府県知事に免許申請を行います。法人登記が不要な分、手続きがシンプルで、短期間で開業できるのが特徴です。
メリット(開業コストの低さ・スピード感)
デメリット(信用力・事業拡大の制約)
法人で宅建業免許を取得する場合
法人設立に必要な登記手続き
法人として宅建業免許を申請する場合、まずは会社設立登記が必要です。
株式会社や合同会社を設立し、法務局で法人登記を済ませた後に宅建業免許の申請を行います。
この順序を間違えると申請ができないため注意が必要です。
メリット(信用力の高さ・融資や取引で有利)
デメリット(設立コスト・維持コストの負担)
登記との関係を理解する
個人開業の場合に必要な登記(開業届・屋号)
個人の場合、法務局での商業登記は不要です。
ただし、税務署へ開業届を提出し、必要に応じて屋号を登録して事業を開始します。
屋号で銀行口座を作ることで事業用資金の管理がしやすくなります。
法人開業の場合に必要な登記(法人設立登記)
法人として免許を取得するには、まず会社を設立し登記する必要があります。
登記事項には本店所在地や代表者、資本金などが記載され、宅建業免許の申請書にも登記事項証明書の添付が求められます。
登記内容と宅建業免許申請の関連性
宅建業免許の申請時には、法人登記の内容と事務所所在地・役員構成などの情報が一致していなければなりません。
例えば事務所移転や役員変更があれば、登記変更と免許内容変更の両方の手続きが必要になります。
不動産独立開業時は個人と法人どちらを選ぶべきか
開業規模や資本金による判断基準
小規模で副業的に始めたい場合やコストを抑えたい場合は個人がおすすめです。
一方で、最初から事務所を構え従業員を雇い、資本金を投じて本格的に事業展開するなら法人の方が適しています。
- 副業的に小規模でできればよい→個人
- 人を雇う・将来的な事業展開を考えている→法人
将来の事業拡大を見据えた選択のポイント
不動産業は取引金額が大きく、信用が重要視される業界です。
将来的に法人化を検討しているなら、最初から法人で始めた方が手続きの二度手間を避けられます。
個人から法人への切り替えは可能か
個人で宅建業免許を取得しても、後から法人を設立し法人名義で免許を再申請することが可能です。ただし再度の申請や保証協会への手続きが必要となり、費用や手間がかかる点には注意が必要です。
宅建業免許取得で注意すべきポイント
専任宅建士の配置義務
個人・法人を問わず、宅建業免許の取得には専任の宅建士が必要です。
代表者自身が宅建士資格を持っていればスムーズですが、雇用する場合には人件費も考慮しなければなりません。
事務所要件と保証協会への加入
事務所は宅建業法の要件を満たす必要があり、単なる自宅やシェアオフィスでは認められない場合があります。また、保証協会に加入する場合は数百万円規模の分担金が必要です。


登録免許税や協会費用などのコスト
個人・法人いずれでも登録免許税として9万円が必要です。
さらに保証協会の分担金や入会金、その他の初期費用を含めると、合計で数百万円の資金が必要になるケースが多いです。
まとめ|個人・法人の特徴を理解して最適な選択をしよう
宅建業免許は、個人でも法人でも取得可能です。
個人は低コストかつスピーディーに開業できる一方で、信用力や事業拡大には限界があります。
法人は設立・維持コストがかかりますが、信用力や融資面で有利です。
また、法人の場合は必ず設立登記が必要であり、その内容が免許申請と直結します。
自分の事業規模や将来の展望を考えたうえで、最適な形態を選択することが不動産開業成功の第一歩となるでしょう。