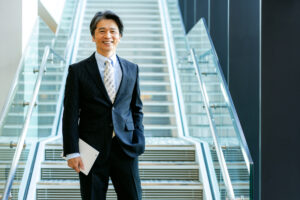専任宅建士が退職したらどうする?法的対応と猶予期間のルール

不動産会社の運営において、専任の宅地建物取引士(以下、専任宅建士)は宅建業免許の維持に欠かせない存在です。特に少人数体制や新設法人では、1人の宅建士にすべてを依存しているケースも珍しくありません。
そんな中で、専任宅建士が退職・休職・解任などで不在となった場合、どのように対応すればよいのか?
本記事では、宅建業法に基づく猶予期間・必要な届出・取引の制限・代替方法など、実務で知っておくべき内容を網羅的に解説します。
専任宅建士が退職するとどうなる?
宅建業者は、事務所ごとに一定数以上の宅建士を置くことが宅建業法で義務付けられています。
その中でも、事務所の常勤従業員5人につき1人以上は専任の宅建士である必要があります。
したがって、専任宅建士がいなくなると、宅建業の「継続条件」を満たさなくなる=業務停止または免許取消のリスクが生じることになります。
猶予期間は「2週間」以内
結論から言えば、専任宅建士の退職後、「2週間以内」に後任を確保して届出する必要があります。
- 宅建業法施行規則第8条の2
- 「専任の宅建士に変更があったときは、変更日から2週間以内に免許権者に届け出なければならない」
この2週間を過ぎても後任が決まらない場合、宅建業者としての免許条件を満たしていない状態になるため、業務停止処分や最悪の場合は免許取消につながる可能性があります。
専任宅建士の不在中にやってはいけないこと
専任宅建士が不在の状態では、以下のような行為が違反対象になります。
1. 新たな媒介契約・売買契約の締結
重要事項説明(35条書面)や契約書の記名押印(37条書面)には宅建士の関与が必須です。不在中にこれらの契約を結ぶと、違法取引と判断される恐れがあります。
2. 宅建士証の返却忘れ
退職した専任宅建士の宅建士証が手元に残っている場合、それを使って書類を作成・説明したと見なされれば、虚偽表示として重大な法令違反です。
3. 専任宅建士がいると“装う”広告や案内
既に退職しているのに、事務所内の標識やHPに「専任宅建士◯◯在籍」などの表記をしている場合、不当表示防止法や宅建業法違反になります。
専任宅建士が退職した場合の対応フロー|退職から再登録までの手順
専任宅建士が退職した場合、次のようなステップで対応します。
1. 退職日を記録し、直ちに社内で共有
正確な退職日(あるいは専任資格を失った日)を記録し、代表者・総務部門がすぐに対応準備を始めます。
2. 免許権者に「宅建士変更届」を提出(2週間以内)
都道府県知事もしくは国土交通大臣(免許の種類による)宛に、「専任宅建士の変更届」を提出します。
- 宅建士変更届出書
- 新しい宅建士の登録番号・氏名・宅建士証コピーなど
- 新旧専任宅建士の関係がわかる書類(退職証明など)
※自治体によって異なるため、必ず管轄窓口に確認をしてください。
3. 新たな専任宅建士の配置と登録手続き
後任となる宅建士を採用・配置し、宅建士証の交付を受けたうえで登録完了する必要があります。即日配置は難しい場合もあるため、候補者がいない場合は早急に採用・業務委託等の対応を検討します。
専任宅建士が見つからない場合の選択肢
一時的な宅建士の採用・提携を検討する
退職後すぐに後任を見つけるのが難しい場合、外部の宅建士と業務委託契約を結ぶ方法もあります。ただし、この場合でも以下の条件を満たす必要があります。
- 常勤である(週5日、事務所に勤務できる)
- 他社との兼務がない
- 事実上、会社の業務に関与している
→ 形式上の“名義貸し”にならないように注意が必要です。


登録実務講習を活用して社内の資格者を育成
専任宅建士候補が未登録の宅建士である場合、登録実務講習(2日間)を受ければ登録可能です。自社内に宅建試験合格者がいるなら、登録までの流れを早急に進めましょう。
よくあるQ&A
Q.「登録だけ先にして、実際の業務は後で」でもOK?
A. NGです。専任宅建士は常勤・実務従事が前提のため、登録だけ済ませて業務には後日着手、というのは違反と判断されます。
Q.「2週間以内なら取引してもいい」?
A. 取引の可否ではなく、「届出が2週間以内」であるだけで、実際の取引は宅建士が不在のまま進めてはいけません。
まとめ:専任宅建士の退職=経営上の緊急事態と認識すべき
専任宅建士の不在は、宅建業免許の根幹に関わる重大な問題です。「2週間」という限られた猶予期間の中で、
- 正確な届出
- 代替人材の確保
- 法令遵守の対応
を迅速に進める必要があります。
特に少人数・個人経営の不動産会社では、宅建士1人に依存するリスクを日頃から認識しておくことが重要です。
将来的なトラブルを回避するためにも、
- 複数の宅建士を確保しておく
- 社内での資格取得を促進する
- 外部支援も視野に入れる
といった体制づくりが、安定した事業運営につながります。
宅建士の退職は避けられないリスクだからこそ、「いなくなったときにどう動くか」をあらかじめ備えておくことが、不動産会社経営者の責任と言えるでしょう。